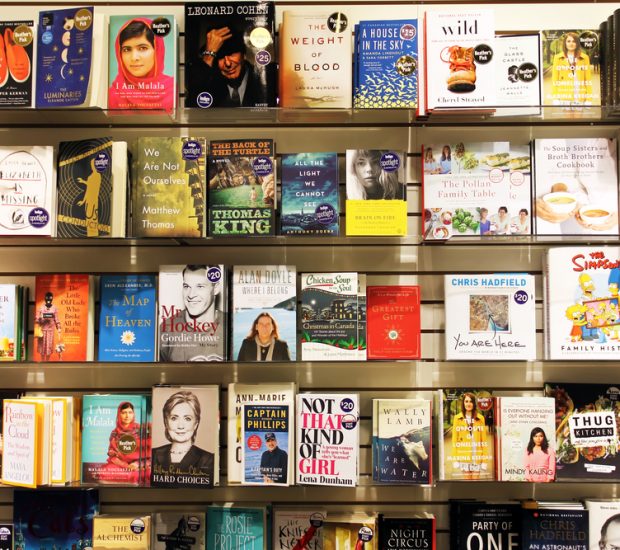最終更新日 2025年7月9日
「出版社の現状が知りたい」
「出版社に未来はあるの?」
「今後、出版社に求められることは?」
出版社は版元と呼ばれており、編集した内容を製本化するまでのノウハウを持っております。
内容はデーター化されて印刷業者に委託され、本になり書店に並ぶことになるのです。
著者を見つけて執筆してもらい売るためには、経験とセンスが必要な仕事であり、タイトスケジュールなことから家に帰れない職業として知られてきました。
その一方で創造的な職業の人気があり、とくに新卒時に有名出版社の入社希望者は数百倍を超えることも珍しくはありません。
https://www.pagcm.org/hatarakiyasuitaisei.html
出版不況が叫ばれている
現在はインターネット時代になり出版不況が叫ばれておりますが、コンテンツを作る能力や企画や編集をするためのスキルの優位性を現在も所有しており、IT化に積極参入するケースや人材の交流も盛んに行われております。
一方で弱小と呼ばれる企業が整理を行って事業を継続しなくなったり、流通を司る取次が倒産するなどのケースも増えているのが特徴です。
時代の転換期に突入して変化できない企業はITの傘下に入ったり、仕事や会社そのものを閉鎖させているのが現状になります。
日本は海外に比べて書籍の価格が低く抑えられており、小売店で販売しても利益率が高くないことが以前から指摘されており問題視されているのです。
一方で出版社から取次から販売店まで、権益を守りながら事業を継続させるシステムを作り上げたことにより、長年利益配分を生むビジネスであったことも間違いありません。
ピラミッド型のマーケットを持っており、下請け構造と返本制度などによって業界を支えてきました。
出版に携わる人間が多かった理由
また下請けは雇用形態が個人事業主やフリーランスであり、労働的な環境は決して恵まれていないと言われていたのが業界のもう一つの特徴です。
それでも出版に携わる人間が多かったことは、クリエイティブワークであり裁量制で高収入が望めたことも背景になっております。
近年はしかしそういった状況がインターネットを代表とするITによって変化を余儀なくされており、出版部数が右肩下がりになると同時に広告費の削減が追い打ちをかけて、出版の利益構造が大きな分岐点を迎えて久しいのです。
現場の労働環境はより過酷になり、以前と違いフリーランスでも高収入を期待出来る人は多くはありません。
そのために優秀な人材が集まり難くなり、プロパーの関係者が高齢化してクリエイティブとしての陳腐化も進んでおります。
相乗的に内容に飽きた読者が本を購読しなくなり、体力や企画力のない出版社から買収や倒産をする流れが出来てしまっているのです。
エンターテイメントやサブカルなどの情報は現在はコンテンツの主流
業界の悪しき慣習が生んだ副作用と言える状況になります。
エンターテイメントやサブカルなどの情報は現在はコンテンツの主流になり、純文学やルポライター作品やノンフィクションは傍流に置かれている現状です。
製作期間や費用投入に比べてリターンが少なく、ビジネスをする上でも旨味がないことが理由となって出版点数が減っています。
以前ならば他のカテゴリーの利益を充当する余裕がありましたが、出版不況により文化的な書籍の発行を守ることが出来なくなりました。
出版社の経営陣やプロパーの社員の見通しの甘さや、下請けを過酷に扱ってきた歴史が現在になって反転している状況です。
今後は企業の統合や淘汰が進み、とくにインターネットのバッティングする分野は壊滅的な状況になります。
たとえば地図の出版社でIT化に乗り遅れた会社などは、淘汰される確率が上昇しており、今後の生き残りはコンテンツホルダーとしてITと手を組むしか道がありません。
編集プロダクションなどの下請けはさらに悲惨な状況
インターネットに接続すればナビゲーションまでしてくれる時代に、一般的な地図が売れる見込みはありません。
需要があったとしても商業的にプラスになるほどの実績は、難しいと言えることは間違いないことです。
版元ですらこの状況なので、編集プロダクションなどの下請けはさらに悲惨な状況になります。
変化に強い企業ならば紙ベースの仕事を減らしてIT化対応をしておりますが、コンテンツを展開してゆくためのノウハウや、仕事を通じて得られる報酬の少なさがネックになり完全な移行が出来ないジレンマ状況に陥っているのです。
こうした状況は業界が変化を望まずに、利益を確保してきた負の遺産になります。
それでも大手企業はコンテンツを作るノウハウや、豊富な資金力で利益を確保しているのです。
今後はハードではなくソフトに市場が変化してゆくと20年前から言われており、印刷などから脱却しつつデジタルメディアと手を組んだ企業の業績は上昇しております。
しかし以前の業界がそうであったように、既得権益を守ることに終始していたビジネスプランでは、状況に変化があった時には対応が出来なくなることも考えられます。
まとめ
日本のエンタメ界の未来への試金石は、変化と正常化にあるのです。
これは書籍だけではなくテレビも新聞も同じであり、ソフトウェアや情報媒体企業がより進化するための取り組みの課題になります。
一つのケースとして地図系の出版企業の今後の動向には注目しておくことをおすすめします。